受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ホーム > 生活・サービス > 届出・証明・旅券・個人番号 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
ページID : 14504
更新日:2025年1月21日
ここから本文です。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
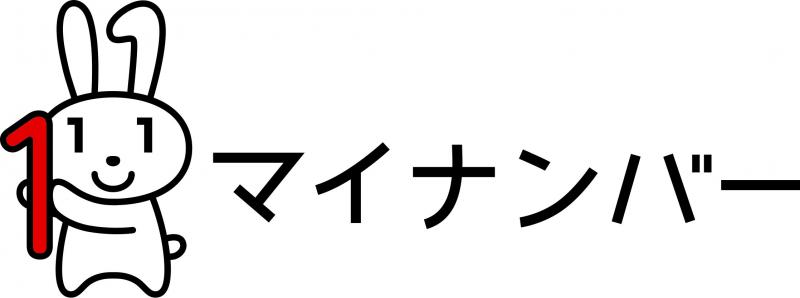
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、行政の効率化を図り、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための基盤となるものです。マイナンバー制度で期待される効果として次のようなことが挙げられます。
| 行政の効率化 |
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。 複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。 |
| 国民の利便性の向上 |
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。 行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることが可能になります。 |
| 公平・公正な社会の実現 | 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行えるようになります。 |
マイナンバーはどのように通知されるの?
平成27年10月以降、住民票を有する世帯に12桁の個人番号(マイナンバー)が記載された「通知カード」を送付しています。
通知されたマイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
マイナンバーはどのような場面で使用するの?
平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが使えるようになります。
(例)
- 年金を受給しようとするとき
- 健康保険を受給しようとするとき
- 児童手当の現況届を出すとき
- 所得税等の確定申告をするとき
- 勤務先や金融機関に税や社会保障の手続きをするとき
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも法律や条例で定められた行政手続でしか利用することはできません。
マイナンバーを他人に提供してもよいの?
マイナンバーは、法律で定められた目的以外に、むやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が他人に不当に提供すると処罰の対象になります。
個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはないの?
個人情報は、これまでと同じように各行政機関等が保有し、必要と認められる場合に限って情報の照会・提供が行われるため、個人情報が特定の機関に集約されることはありません。
行政機関や地方公共団体を監視・監督する第三者機関の設置、マイナンバーの利用事務ごとに義務付けられる特定個人情報保護評価、マイナンバーに関する個人情報漏えいに対する罰則強化など、様々な保護措置が実施されます。
個人番号カードとは
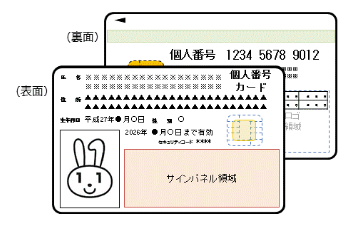
平成28年1月以降、希望者に「個人番号カード」を交付しています。個人番号カードは身分証明書としても利用できるほか、個人番号を確認する場などで利用されます。個人番号カードと個人番号カードに搭載されるICチップには、本人の「マイナンバー」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「顔写真」などが記録されます。
※所得情報などプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
法人番号とは
法人には13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。