受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 19613
更新日:2025年2月26日
ここから本文です。
ハラスメント防止のために
セクシャルハラスメントやパワーハラスメントは、相手の人権を無視した不快感を与える行為で、重大な人権侵害です。
職場におけるセクシャルハラスメント(セクハラ)とは?
セクハラとは、性的な言動により相手の人間性を傷つけることをいい、そのことによって相手が不利益を受けたり、不快な状況になったりするものです。
基本的人権を著しく侵害し、男女がともに個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現を妨げるもので、決して許されるものではありません。
「男らしい」「女らしい」など固定的な性別役割分担意識に基づいて言動は、セクハラの原因や背景となってしまう可能性があります。以下のような言動は、無意識のうちに言葉や行動に表れてしまうものです。管理職の方は、日ごろから自らの言動に注意するとともに、部下の言動にも気を配り、セクハラの背景となりえる言動についても配慮することが大切です。
『注意する言動』
- 「男のくせにだらしない」「家族を養うのは男の役目」
- 「この仕事は女性には無理」
- 「子どもが小さいうちは、母親は子育てに専念すべき」など
セクハラの種類
職場におけるセクハラには「対価型セクシャルハラスメント」と「環境型セクシャルハラスメント」があります。
対価型セクシャルハラスメント
労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受けることです。
たとえば、
- 事務所内で経営者が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇すること。
- 出張中の車内で上司が労働者の腰・胸などに触ったが、抵抗されたため、その労働者にとって不利益な配置転換をすること。
- 社内で経営者が、労働者の男女関係について公然と発言していたが、抗議されたため、その労働者を降格すること。
環境型セクシャルハラスメント
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。
たとえば、
- 事務所内で上司が労働者の腰・胸などを度々触ったため、その労働者が苦痛に感じ就業意欲が低下すること。
- 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手につかなくなること。
少しでも不安、悩みがある場合は、まずは相談してください。
会社・職場の相談窓口
男女雇用機会均等法及びそれに基づく指針により、事業主は、セクハラ防止のために相談窓口を設置することが義務付けられています。
お困りのときは、まず職場の窓口にご相談ください。
その他の相談窓口
職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)とは?
職場のパワハラは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為のことです。
上司から部下への行為に限ったものではなく、先輩・後輩や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。
また、個人の受け止め方によって不満に感じる指示や注意・指導があっても「業務の適正な範囲」内であればパワハラには該当しません。
職場のパワーハラスメント(6つの類型)
(1)身体的な攻撃(暴行・傷害など)
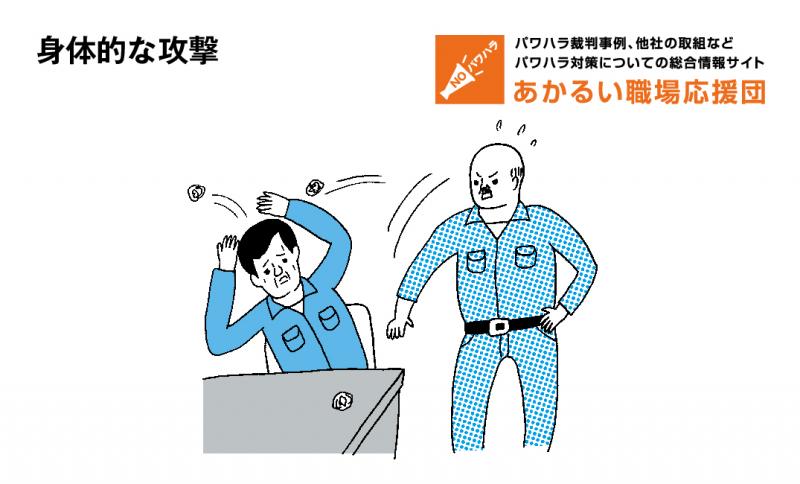
(2)精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言など)

(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視など)

(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力と経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

パワハラを受けたら
「はっきりと意思を伝えましょう」
ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善しません。「やめてください」と、あなたの意思を伝えましょう。
黙っていると事態をさらに悪化させてしまうことがあります。問題を解決していくことが、同じように悩んでいる人を救うことにもつながります。
「会社の窓口に相談しましょう」
会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。労働組合に相談する方法もあります。
社内に相談相手がいないときは、ひとりで悩まず、相談機関へ相談しましょう。